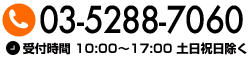- TOP
- 経営と組織の改善のために
- 適正な人事評価のために必要な定性評価と定量評価とは
適正な人事評価のために必要な定性評価と定量評価とは
違いを知っておこう

人事の仕事の一つに、従業員の評定がありますが、その方法も様々です。
その方法の中でも定量評価と定性評価がありますが、違いを知り適切に使い分けなければなりません。
定性評価は欠かすことのできない重要な方法として人事の中でも広く知れ渡っているでしょう。
これは、数字で表すことができないものを見極めるものです。
例えば、営業マンは契約数や売り上げなど数字で判断することができますが、契約後の事務作業をしている社員の取り組みや努力はなかなか数字で表すことができません。
事務作業も効率よく行うための工夫をしていたり、スキルや知識も必要であるため、裏方で動いていたりする人にもスポットを当てるべきです。
このようなポジションにいる人を定性評価で計ることができます。
しかし、これだけでは全ての社員を査定することができないため、通常は定量評価と組み合わせて行います。
2つを組み合わせる

定量評価は数値で達成度を見るもので、具体性がありわかりやすく、従業員も納得しやすいという特徴があります。
一般的には、売り上げや受注件数など目でわかるもので判断しますが、定性評価と組み合わせて総合的にアセスメントすることが大切です。
どんなに売り上げや受注件数が多くても、勤務態度が悪ければ表彰されるべきではありません。
遅刻や早退、欠勤など勤務態度と合わせて総合的に決めると精度が高く公正なアセスメントになります。
人事が公正に行えば、社員のモチベーションアップや維持につなげることができるでしょう。
公正に行うためには明確な基準が必要です。
基準が曖昧で人事の裁量だけに任せると客観性や公平性に欠け、不満を抱く従業員が増えます。
これは退職者を増やす原因となるため、注意しなければなりません。
基準を設定する際は、数値で表せないものに対してはスピードや創意工夫、知識、規律性、積極性、責任感、協調性などをベースに、数値で表せるものには個人やチーム、部署それぞれが目標に向かって果たすべき役割を考えて、厳しすぎず簡単すぎない数字の目標を設定するといいでしょう。
目標が全てにならないように、達成まで自主的に取り組めるように支援することも必要です。